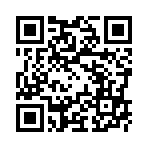2011年06月12日
陶芸家さんの週末おうちカフェ@有田

佐賀新聞のFITに「おうちカフェ」の特集で紹介されていた
有田町の陶芸家さんが金、土、日の週末だけ、コーヒーと
手作りスイーツをだしている、おうちカフェに行ってきました。
陶芸家さんのカフェですから、コーヒーカップやお皿などは
全部がそこで作った食器で、写真のコーヒーカップもそうです。
ふだんは工房や展示室として、使っているスペースを週末だけ
カフェに変身してるのですが、落ち着いた隠れ家的な
陶芸家横田さんおうちカフェは「カフェ・グルニエ」。
おいてある椅子はトーネットの曲げ木の「コーヒーハウスチェア」。
現代デザイン史には登場する、曲げ木の椅子とカフェ空間は
よく似合っています。
他の窯元さんも「週末だけのピザ屋」とか、ラーメン好きな窯元なら
週末だけのラーメン屋など、みんな「器」を作っているんだから
ラーメンのメニューはひとつでも、ラーメン鉢はいろんな種類があり
好きなラーメン鉢を選んでもらい、限定ラーメンを食べると、たぶん
お客さんも喜ぶんじゃないかと思うけどね。
2011年05月11日
化粧水ボトルが佐賀新聞で目立ってます。
連休も終わり昨日は一日中、ズ~ッと雨風の伊万里。
この雨は恵みの雨ですから、ありがたいものです。
ありがたいと言えば、今朝の佐賀新聞を見たら、ありがたい
ニュースを見つけました。
昨年に伊万里鍋島焼窯元の虎仙窯さんが開発した、化粧水ボトルが
この4月から本格的に販売されたニュースが紹介されており
しかも「赤枠」で囲ってあるから、これは目立つね。
商品開発を手伝った一人としても嬉しいニュースです。
ただ写真と記事が書いてあるだけでなく、よく目立つように
紹介されているから、こうゆう配慮はほんとにありがたい。
いくら商品が良くても、その商品が存在している情報を、より
多くの人たちに「知ってもらう」ことが大事。
知ってもらうために広告宣伝をするのはお金がかかりますから
記事として、こうして取り上げられるように仕掛けてみるのも
ひとつの方法です。
いつも新商品を見慣れている新聞記者の目からも、化粧水ボトルが
それなりの評価をもらったから、きっと掲載されたのでしょう。
2011年04月22日
記者発表した伊万里焼化粧水ボトル・花しずく
伊万里鍋島焼の窯元・虎仙窯さんが作った化粧水ボトルの記者発表を
今日の午後から、佐賀県庁の記者会見室でするのを手伝ってきました。
伊万里鍋島焼化粧水ボトルの名前は「花しずく」。
昨年、佐賀県の産地再生補助事業に申請し、採択され、今年の2月には
試作品を完成して、4月より本格的に販売が始まりました。
有田陶器市が近いから、虎仙窯の化粧水ボトルを焼き物ファンに
知ってもらうには、良いタイミングの記者発表です。
新商品を開発する相談が、昨年の3月ごろに虎仙窯さんからあり
新規性や市場性などの点からも、産地再生支援事業の対象には充分に
あてはまっているので、事業計画づくりから申請書の作成などを
サポートしていた。
県庁の担当者に「花しずく」の記者発表の機会を、なんとか
有田陶器市の前にできないかとお願いして今日の22日になりました。
伊万里焼化粧水ボトル・花しずく。
大きく花が開いてほしいものです。
2011年02月11日
有田の雛ご膳・雛のやきものまつり
小雨が時おり降ったり止んだりですが、伊万里の隣の有田町で
今日から、「雛のやきものまつり」が始まっています。
お昼に立ち寄ったのは、雛のやきものまつり期間、土日祭日限定で
有田にちなんだ料理を出してくれる「小路庵」へ。
ここは辻製磁社のすぐ手前にある旧家を利用し、有田の元気なグループ
「有田町づくり女性懇話会」の皆さんが手作りの料理を出してくれます。
おいしい食事の後は表通りを歩かないで、トンバイ塀を見ながら
裏通りをぶらぶらと。


2011年01月21日
鍋島焼の新作の「色鍋島かっさプレート」。

今日の午前中に出かけた先で見せられたのが、写真の
伊万里鍋島焼で出来た、「色鍋島かっさプレート」。
「かっさ」なんて言葉を知ったのも初めてだし「かっさプレート」を
目の前で見たのも、触ったのも60年の人生で初めての初体験。
「かっさ・活沙(本当はもっと難しい漢字)」とは、中国で2500年ほど
前から使われているマッサージの道具で、水牛の角や水晶などもあり
リンパマッサージに適しているようです。
これを作ったのは勿論、鍋島焼窯元さんなのですが、商品を企画して
形状や大きさなどを考案して販売しているのは、伊万里の床屋の
オヤジさんです。
ですが、ただの床屋のオヤジさんでなくて、エステシャン30年の
経験もあり、オリジナルのこだわり化粧品「MKコスメテック」も
作ってるし、理容業のカット講師を指導する委員もしていますから
ただの床屋さんではありません。
そんな経験豊富なプロエステシャンが自信をもって、考えて作り
販売を始めたばかりの新商品が「色鍋島かっさプレート」です。
詳しいことは⇒サロンド・マツナガ 0955-28-2640
2011年01月11日
伊万里焼の化粧水ボトル
新年になっても有田焼などの陶磁器業界の低迷が変わらず続いて
いるようですが、それは昨年と同じような事を今年もしようとすると
低迷がまだ続きますよという、注意信号のサインなんです。
有田焼の陶磁器は割烹食器をはじめ、一般食器などの食器分野が多いので
何か新しい商品を開発しようとする場合には、
(A)食器分野が低迷しているので、食器以外の分野を開発する。
(B)食器分野が低迷していても、やはり食器分野に依存しているから
今までと違う、新しい食器を開発する。
のように、2つの考え方があるようです。
今日の写真は(A)のように、食器以外の商品を考えた伊万里鍋島焼の窯元
虎仙窯さんが開発した化粧水ボトル、その名称は「花しずく」。
この名称も虎仙窯のスタッフ皆さんで色んな名前のアイデアを
出し合って決めて、みんなで取り組むのがイーデスね。
化粧水ボトルの開発は佐賀県の産地再生補助事業に申請して採択され
昨年の7月頃から商品開発に取り組まれましたが、採択されなくても
取り組むつもりだったと聞いてますから、化粧水ボトルは本気です。
柔らかそうな形状やシンプルで、持ちやすそうな印象を受けます
スプレー部品などは今までに扱っていないため、専用の箱など余計な
仕入れ部品が増えることになり、食器分野以外の商品を開発すると
今までにないリスクを背負う事になるけど、何もしないリスクよりは
新たなお客と出会うチャンスが増える事につながります。
どんな商品であれ、新しいアイデアやデザインを思いついたら、試しに
作って見ることです。そして大事なのは、お客(市場)の声を聞いて
素直に「改良」することなんですが、お客の声には色んな声があるけど
耳障りがいいのよりは、耳が痛くなる声がどうも本当の声のようです。
*ホームページはこちら⇒虎仙窯
*化粧水ボトルのブログは⇒虎の子の道
2010年11月27日
伊万里鍋島焼のテーブルコーディネート展
江戸時代の大庄屋だった、伊万里の前田家住宅で開催されている
鍋島焼窯元おかみさんたちの「テーブルコーディネート展」を見てきました。
今回のテーマは、「華のある食卓」。それぞれのテーブルには
季節の「花」をモチーフにした器がコーディネートされています。
どんな器が出されているのに関心が行くものですから、写真も
器が中心になってしまいます。
庭の紅葉もきれいで、明日までの開催ですからぜひお出かけください。











下のテーブルは「キッズ」作品。

鍋島焼窯元おかみさんたちの「テーブルコーディネート展」を見てきました。
今回のテーマは、「華のある食卓」。それぞれのテーブルには
季節の「花」をモチーフにした器がコーディネートされています。
どんな器が出されているのに関心が行くものですから、写真も
器が中心になってしまいます。
庭の紅葉もきれいで、明日までの開催ですからぜひお出かけください。











下のテーブルは「キッズ」作品。

2010年11月05日
鍋島焼伝統工芸士・巒山窯の繊細な絵付け
伊万里鍋島焼の里・大川内山では、藩窯秋まつりが今日まで開催中。
大川内山の伝統産業会館で展示している「鍋島焼窯元おかみ会の
テーブルコーディネート展」を見に行ってきました。


写真の器は、「巒山窯・らんざん」です。
窯元には、絵付け部門で「伝統工芸士」の資格を持つ人たちが
いますから、筆による絵付け技法は素晴らしく、「すごい!」
なんてより、出る言葉は「スンゴ~イ!」
繊細な濃淡の色具合と線の細さ、そして独自の呉須色といい
伊万里鍋島焼は同じですが、窯元によってそれぞれ「個性」が
あるので、窯元めぐりが楽しくなりますね。
藩窯秋まつりはこちらから⇒ 伊万里鍋島焼協同組合
大川内山の伝統産業会館で展示している「鍋島焼窯元おかみ会の
テーブルコーディネート展」を見に行ってきました。


写真の器は、「巒山窯・らんざん」です。
窯元には、絵付け部門で「伝統工芸士」の資格を持つ人たちが
いますから、筆による絵付け技法は素晴らしく、「すごい!」
なんてより、出る言葉は「スンゴ~イ!」
繊細な濃淡の色具合と線の細さ、そして独自の呉須色といい
伊万里鍋島焼は同じですが、窯元によってそれぞれ「個性」が
あるので、窯元めぐりが楽しくなりますね。
藩窯秋まつりはこちらから⇒ 伊万里鍋島焼協同組合
2010年11月04日
畑萬陶苑さんの「おもてなし」と「鶴の器」
img src="http://blog.sagafan.jp/usr/design/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E5%86%99%E7%9C%9Fs116.jpg" alt="" >
10月下旬から11月初旬にかけて、有田や伊万里などの
焼き物産地ではイベントがあるため、このブログに書く記事にも
焼き物関連が続くことになります。
伊万里鍋島焼の「藩窯秋まつり」は、11月5日(金)の明日まで
開催しており、畑萬陶苑さんに立寄って
新作を見た後「お茶でもどうぞ~」と出されたのが
写真の「おもてなし」です。
おもてなし3点を載せている器は、「鶴」の絵柄ですが
いかにも鶴ですというような鶴を横から見た立ち姿ではなく
鶴を真上から俯瞰しているようで、左側には上から見える
「頭」の部分。こういう構成をした鶴の表現は面白いですね。
また、お皿の形状も単なる「楕円」ではなく、頭側の方が
すこしばかりすぼんだ、大きな卵の形をして
縁起の良い器に仕上げてますね。
器の形と、白磁のスペースをうまく活かした青磁との割合など
全体がとても上品な出来映えになっています。
畑萬陶苑さんのHPは⇒ 畑萬陶苑
10月下旬から11月初旬にかけて、有田や伊万里などの
焼き物産地ではイベントがあるため、このブログに書く記事にも
焼き物関連が続くことになります。
伊万里鍋島焼の「藩窯秋まつり」は、11月5日(金)の明日まで
開催しており、畑萬陶苑さんに立寄って
新作を見た後「お茶でもどうぞ~」と出されたのが
写真の「おもてなし」です。
おもてなし3点を載せている器は、「鶴」の絵柄ですが
いかにも鶴ですというような鶴を横から見た立ち姿ではなく
鶴を真上から俯瞰しているようで、左側には上から見える
「頭」の部分。こういう構成をした鶴の表現は面白いですね。
また、お皿の形状も単なる「楕円」ではなく、頭側の方が
すこしばかりすぼんだ、大きな卵の形をして
縁起の良い器に仕上げてますね。
器の形と、白磁のスペースをうまく活かした青磁との割合など
全体がとても上品な出来映えになっています。
畑萬陶苑さんのHPは⇒ 畑萬陶苑
2010年11月03日
有田町うーたん通りの「福珠窯」で、ぜんざい。
今日の伊万里は朝から青空が広がって、出かけるにはいい天気。
有田町のうーたん通りでは、「秋の窯まつり」をしているので
東京の友人から頼まれた器を買いに、指定された有田焼窯元の
「福珠窯」へ出かけてきました。
駐車場には福岡や長崎、佐世保など近県ナンバーの車がとまって
福珠窯の展示場はお客さんで混んでましたね。
友人から頼まれた器を買ったら、隣りにある福珠窯が経営している
「茶寮・風のかまえ」で、ぜんざいを食べて小し休憩~。
ぜんざいを入れている器は、もちろん福珠窯の食器でした。
部屋から見える紅葉を楽しむには、もう少し冷えてからですね。
2010年10月30日
限定ランチは波佐見の陶郷・中尾山で

伊万里や有田の周辺にも、焼き物の里がいくつかあり、有田の
隣り町、長崎県波佐見町の中尾山は「陶郷」と名乗ってます。
20近くある窯元の有志で秋陶祭が行われていて、先週末に
立寄ってきました。
紅葉にはまだ早いけど、散策するには手頃な広さです。
限定ランチを食べたのは「陶房・青」の吉村製陶所さんです。
ランチの食器は、すべて陶房・青さんで作っている器で、大きな
楕円はカレー皿。片側だけのフチを広くとって、すくい易い
形状にしてあり、確かにすくい易かったですね。
中尾山の窯元は一般の食器作りが中心ですから、普段の食卓に
使う食器を探すには手頃な値段の器が多くあり、蔵出しモノも
あるので、焼き物好きなお客さんで賑わってました。
歩いている人たちを見ると、年齢の若い人たちが多くいて
なだらかな坂道を歩きながら窯元めぐりをお勧めします。
陶房・青さんのHPは、見やすくできているので焼き物好きな方は
クリックして見ては。⇒ 陶房・青
2010年06月11日
日経MJに伊万里ルーペ
仕事がら読んでいる新聞の日経MJ。
MJはマーケティング・ジャーナルの頭文字のMとJ。
マーケティングは販売と密接ですから、売上を上げようとするには
どうすれば売れるかの「マーケティング」をしっかりすることが大事。
いい商品を作れば売れるだろうの、「だろう」開発は怪我の元になり
開発している本人や関係者が、「これは良いね」といくら自画自賛しても
顧客やマーケットが、その良さを判断する決定権を持ってますから。
この間、記者発表して、佐賀新聞や朝日新聞、サガテレビなどで
紹介されていた伊万里焼ルーペ。
今日6月11日の日経MJに、新製品ページで紹介されてました。
今度は全国版ですから、いいキッカケになると、いいですね。
詳しいことは、こちらから ⇒ 伊万里焼ルーペ
2010年05月05日
有田陶器市で柿右衛門窯と深川製磁へ

今日、5月4日も青空が広がって、夏のような暑い一日でした。
東京から来ている知人を、有田陶器市にご案内~。
有田の街中は混んでいるので、有田焼といえば色絵の柿右衛門
ですから、まずは柿右衛門窯へ。陶器市の期間中だけは
数奇屋風家屋でお茶のおもてなしがあり、これは嬉しいね。
「柿の木」の前で記念写真を撮っている観光客もいました。

そして、ランチもかねて深川製磁のチャイナオンザパークの美術館と
アウトレットへ。有田陶器市だけの限定ランチがあり、その名も
究林登カレーと究林登バーガー。
有田陶器市には普段にはない色んなサービスがありますね。
それにしても、夏のように暑いので、汗が流れる陶器市です。
2010年05月01日
龍馬が使った茶碗と三川内焼

今日は天気もよく、有田陶器市はかなり混んでいそうですから
有田を通り過ぎて、隣りの長崎県佐世保の「三川内焼」で
はまぜん祭りという陶器市をやっているので足を伸ばした。
13軒ほどの窯元がいて、こじんまりとした山里は気持ちよく
窯元の展示場を覗いていたら、「龍馬の使った茶碗のレプリカ」と
書いてある茶碗が置いてあった。
ちょっと小ぶりな丼で、フタにも「龍」、茶碗にも「龍」が描かれて
いるから、これを龍馬が使ったといわれたら、納得するしかない。

それにしても、三川内焼と龍馬との縁があったとは。
福山龍馬の魅力とNHK大河ドラマの影響は大きいね。
2010年04月12日
深川製磁の直営レストラン
有田焼を代表するメーカーの深川製磁。ここの工場の敷地内には
美術館やショップ、そしてレストランがあり、チャイナ・オンザ・パーク
とよばれて観光バスもやってくる、有田の観光地のひとつ。
レストラン究林登(クリント)は深川製磁の直営レストランですから
当然使われる食器は深川製磁製。まさに「食と器」を実践している。
写真はデザートに出てきたケーキとプレートです。スタッフの人に
「可愛いプレートですね」と声をかけたら
「このプレートで出すと、皆さんから言われます」と嬉しそうな声がきた。
ケーキの話よりもプレートの話になって、食事の後にショップへ行って
買い求めるお客さんがいるようで、ここのレストランは食事だけでなく
食器のプロモーションセンターの役割りもしている。
店の中に、食器をスキマなく置いていれば事足れりの時代ではなく
食器の良さを「伝える」努力の方向が良いと、売れていくようですから
売れない原因は、回りのせいだけでなく、努力の仕方と工夫です。
2010年04月02日
続・伊万里焼納めの器
昨日の続きで、伊万里の大川内山「春の窯元市」から展示販売して
いる、「納めの器」を紹介します。
絵付け伝統工芸士の技がさえる、「巒山窯・らんざん」さん。
深い緑色に特長がある鍋島染付と、繊細な線描き作品です。

そして、次は「文三窯・ぶんぞう」の三宅製陶所さん。
東京ドームのアンケートでも、一番人気の高かった器で
藍色の鍋島染付で、花模様が上品に描かれています。

淡い水色が特徴的な器は、「杏土窯・あづち」さん。
水色のところが少し盛り上がった優しい表情で、これも人気が高い。

そして、季節のアヤメを描いているのは、「畑萬陶苑・はたまん」さん。
色鍋島の色使いを基調にして、涼しげに仕上げています。

同じような形状の器ですが、それぞれ窯元さんの個性が出ており
見ているだけでも楽しいですね。
大川内山の桜は、週末までは見頃ですから、焼物の掘り出し品を
探しがてら、散策されてはいかがですか。
いる、「納めの器」を紹介します。
絵付け伝統工芸士の技がさえる、「巒山窯・らんざん」さん。
深い緑色に特長がある鍋島染付と、繊細な線描き作品です。

そして、次は「文三窯・ぶんぞう」の三宅製陶所さん。
東京ドームのアンケートでも、一番人気の高かった器で
藍色の鍋島染付で、花模様が上品に描かれています。

淡い水色が特徴的な器は、「杏土窯・あづち」さん。
水色のところが少し盛り上がった優しい表情で、これも人気が高い。

そして、季節のアヤメを描いているのは、「畑萬陶苑・はたまん」さん。
色鍋島の色使いを基調にして、涼しげに仕上げています。

同じような形状の器ですが、それぞれ窯元さんの個性が出ており
見ているだけでも楽しいですね。
大川内山の桜は、週末までは見頃ですから、焼物の掘り出し品を
探しがてら、散策されてはいかがですか。
2010年03月26日
続・納めの器

前回の記事は、こちらから
伊万里鍋島焼の「納めの器」を開発する時、伝統工芸士の資格を
持つ窯元さん達は、絵付けの技を見せようとがんばって、たくさんの
絵付けをする傾向があるので、今の「食卓に合う」ような絵付けを
心がけるようにアドバイスしたのです。
そして、出来上がった試作品を昨年の秋に展示しアンケートを取り
さらに改良したモノを、2月のテーブルウェア・フェスティバルに出して
首都圏の焼き物ファンのお客さまに見てもらい評価を受けたのでした。

当然ですが、同じ形でいろんな絵付けがありますから、女性客に人気が
ある食器と、そうでないモノとがあり、こうして集めたアンケート情報を
参加した窯元さんにオープンにして、次に改良する場合や食器作りの
ヒントになるようにサポートをしてきました。
それを更に改良し、4月1日(木)から始まる「春の窯元市」から
販売するので、どんな絵柄に仕上がっているのか楽しみですね。
春の窯元市については→伊万里鍋島焼協同組合