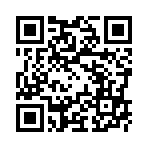2011年12月02日
今年のグッドデザイン賞
今年の十大ニュースには早いけど、私的な重大ニュースには
デザインを手伝った食器がグッドデザイン賞を受賞した事があり
昨日、伊万里市役所の記者クラブでの記者発表に
同席させてもらった。

作品名:青白磁「一段」
その透明感と形の美しさもさることながら、実際に手にすると
「段」が指にすいゆくような感触があり、使いやすい。
伝統のものの良さを現代の食卓に使いつづけることを奨励する
すぐれた製品群だと思う。(審査員の講評)
食器のデザインへの思いを、しっかりと理解していただいた
審査員の評価コメントはありがたく、嬉しく、励みになるし
還暦を過ぎたオッサンですが、ほめられると素直に嬉しいね。
デザインの作業はイメージしたのをスケッチや図面に描くだけ。
ですから、新しいデザインを考え、生み出す作業は簡単です。
それに比べ、実際に「作る」ほうの仕事が大変な作業ですから
食器作りにチャレンジした窯元の虎仙窯さんの努力と技術の評価が
グッドデザイン賞だと思っています。
デザイナーは裏方でデザインした商品が表に出ると嬉しいね。
2011年10月25日
スマートなデザインのナイフ
ナイフの刃渡り部分と、手に持つところでは、見てのとおり
ホールド部分が細く、ちゃっちくて頼りなさそうな印象。
一般的なナイフのホールド部分は、刃渡りと同じような幅で
中が中空構造のタイプを多い。
頼りなさそうなナイフだなと思って、実際に持ってみたら
ホールドは細いけどホールド断面の形状が半円になって
しっかりして持ちやすいんだな。これが。
細いけど、金属のかたまりなので、重さのバランスもよく
指のなかでの納まりもいいから、これは使いやすい。
特に刃渡り部とホールド部の「合わせの納まり」に、この
ナイフのデザインが集約されていると思う。
見た目は、細くて頼りなさそうだからと、見た目だけで
物事を判断しちゃいけない。と、ナイフを見て反省。
見た目の印象が大事なんだと日頃から言ってますがね。
「とらわれず・こだわらず・かたよらず」のフラットで
ニュートラルな視点を忘れんようにせんばです。
2011年10月20日
審査員からほめられた器

青白磁・一段「ぐい呑み」
以前から鍋島青磁の透明感ある美しさを、器にどうデザイン
しようかと、アイデアスケッチを描いていました。
暮らしのなかで、一番使うだろう「湯呑」は山ほどあるから
青磁釉薬の美しさを表現する「カタチ」を考える前に、普段に
使っている煎茶碗(そば猪口ですが)を手に持って、お茶を
飲むたび酒を飲むたびデザインを考えてはスケッチを描いた。
食器は文字通り「食の器」なので、使いながら考えるとなると
1日に少なくとも3回は嫌でも考える癖がついてしまう。
そして、いくつか描いたデザインの中から、窯元さんと一緒に
作った食器が今年のグッドデザイン賞を受賞しました。
受賞できたのは窯元・虎仙窯さんの技術と努力のおかげで
細かいことを言っては試作を作ってもらいました。感謝。
グッドデザイン賞・審査員の評価
=その透明感と形の美しさもさることながら、実際に手にすると
「段」が指にすいつくような感触があり、使いやすい。
伝統のものの良さを現代の食卓に使いつづけることを奨励する
すぐれた製品群だと思う。
2011年10月05日
グッドデザイン賞を受賞した器
10月3日に今年のグッドデザイン入賞が公開されました。
デザインを手伝った青白磁の食器シリーズが入賞した。
今までなかったのが不思議に思えるようなものが
優れたものだと思います。
その潜在的にみんなが思っていた「解」が具現化された
ときに、グッドデザインは生まれます。
なんて話しているのは、今年のグッドデザイン賞の
審査委員長をしているデザイナー深澤直人さん。
丸い加湿器やインフォバーのデザインをしてます。

グッドってのは、文字どおり「良い」わけですから
今現在、世の中にある物よりも、どこかが良いということ。
暮らしに役立つものを生み出す「行為「がデザインだから
見たときに「あ~、きれい!」とか、「これってイイネ」と
そこに笑顔が生まれるだけでグッドでしょ。
「GOOD・良い」という意味を、自分なりに解釈して
言い換えれば、「快適さ」という意味もあるように思う。
快適とか適正などのように、暮らしを快適にしてくれる
役割をちゃんとはたしてること。
それがグッドデザイン。しかも適正な価格で。
グッドデザイン賞を受賞したのは、伊万里鍋島焼窯元の
虎仙窯さんの青白磁の器。おめでとうございます。
佐賀県内でグッドデザイン賞に入賞したのはこれ1件。
*今年のグッドデザイン賞は→こちらから
デザインを手伝った青白磁の食器シリーズが入賞した。
今までなかったのが不思議に思えるようなものが
優れたものだと思います。
その潜在的にみんなが思っていた「解」が具現化された
ときに、グッドデザインは生まれます。
なんて話しているのは、今年のグッドデザイン賞の
審査委員長をしているデザイナー深澤直人さん。
丸い加湿器やインフォバーのデザインをしてます。

グッドってのは、文字どおり「良い」わけですから
今現在、世の中にある物よりも、どこかが良いということ。
暮らしに役立つものを生み出す「行為「がデザインだから
見たときに「あ~、きれい!」とか、「これってイイネ」と
そこに笑顔が生まれるだけでグッドでしょ。
「GOOD・良い」という意味を、自分なりに解釈して
言い換えれば、「快適さ」という意味もあるように思う。
快適とか適正などのように、暮らしを快適にしてくれる
役割をちゃんとはたしてること。
それがグッドデザイン。しかも適正な価格で。
グッドデザイン賞を受賞したのは、伊万里鍋島焼窯元の
虎仙窯さんの青白磁の器。おめでとうございます。
佐賀県内でグッドデザイン賞に入賞したのはこれ1件。
*今年のグッドデザイン賞は→こちらから
2011年08月30日
グッドデザイン賞の現物審査

この間の8月25日と26日、東京ビッグサイトでは
グッドデザイン賞の現物審査があり、東京にいる友人に
手伝ってもらい、新作の食器を展示しました。
審査員はデザインのスペシャリストばかりですから、審査台に
ただ現物をポンと置いて、はい終わりとはいきません。
審査員は言い換えるとお客さま。その場で初めて多くの現物を
見ることになりますから、印象良く見せて「これはいいね」と
思ってくれるように、現物の「良さ=特長」を、どうやって
見せるか、印象づけるかといった、見せ方の工夫ひとつにも
デザイン力が試されます。しかもコストをかけないで
限られた条件のスペースですから。
こうした審査での「見せ方の工夫」をすることで、その商品を
お店で実際に展示販売する時に、見せ方の工夫が活きてくる。
モノがあふれている時代ですから、お店の展示台にポンと
商品を置いて値段を見せるだけで、その商品の良さ=価値が
初めて見るお客に伝わるでしょうか。
なかなか売れんねと愚痴を言うヒマがあるなら、「見せ方」や
「伝え方」の知恵をだし、もっと工夫せんば。
2011年07月23日
グッドデザイン現物審査の準備
グッドデザインの第一次審査をパスした事業所で、次の現物審査に
提出する商品の制作について、午後から打ち合わせをしてきた。
審査用の良品現物をすぐに作りに入らないと、次の締め切りまで
時間にあまり余裕がないので、早めに作りこみをするためです。
まあ、アドバイスというほどではないのですが、審査員は全員が
デザインについてのプロ集団だし、今までに優れた品を見慣れて
いる連中が、「これはいいね」と感じてくれるようにするには、どこに
ポイントがあるだろうかと試作品を見ながら、この辺が大事だろうとか
たぶん、ここもポイントになるだろうと、あくまでも「だろう想定」での
話しになった。そりゃあ、グッドデザイン賞に入賞するにも大事ですが
商品が今の時代に、「これはいいね」と言われるような価値を探して
見つけて、自分で考え、自分で作るほうがもっと大事だと思うし
第一次審査をパスできたのは、デザインとか書類の文章のできばえ
よりも、運が良かったんだと思うから、運の良さにサンキュウだね。
2011年07月20日
グッドデザインの第一次審査合格!

今年のグッドデザイン賞に応募するのをサポートした事業所から
無事に写真と書類の第一次審査を合格した連絡が今日にあった。
未公開なので、モノを詳しく説明ができませんのであしからず。
まだ、これから肝心の現物審査がありますから、第一次審査を
合格したと浮かれるわけにはいきません。通過点ですから。
第二次審査の現物審査の締め切りが8月下旬なので、現物の
出来映え次第がグッドデザインへの入賞を左右するので
さらに詳細な姿、カタチを検討する必要があります。
グッドデザインに入賞すれば、それは素直に嬉しいことだけど
それよりも今までと違う対象にトライすることで、今までと
また違った視点で商品を見つめるキッカケになり、新しいモノを
デザインしようとするなら、まず「気持ちを新しく」しないと。
何かをしようと思うなら、どうしようかと迷っている言い訳を
並べるよりも、まずは何でも「トライする」ことで
きっと何かと出会えるのは確かだと思う。
2011年07月16日
グッドデザイン賞のハサミを見ながら

ここ最近、夜のミーティングが続いたせいか、机の中の整理が
できなかったので、少しはしようと片付けていたら、以前に
グッドデザイン賞に選ばれた美容ハサミの箱を見つけた。
中には、未使用のまんまのハサミが入っていて、ちょっと髪を
切ったみたけど、切れ味は変わらずに、よく切れる。
鋏の特長が、刃先にチタンコーティングしていること。
そして出来たのが、「面取りした刃先」のデザインです。
ハサミの原理は変わらないし、基本形が完成されているので
他とは違う点(個性)をどうやって表現すると、いい感じになるかと
アイデアスケッチを描いては面取りの幅や曲線など、いくつかの
試作品を作っては修正するその繰り返しをすることで
見えない「姿」が見えてきたのです。
最初に浮かぶイメージなんてのは、ぼやっとしたものなんですが
試作品を作っては直すのを繰り返すことで、でぼやっとしてたのが
だんだんとクリアになるから、微妙な試作を繰り返しすることで
ある瞬間に見えない姿が「これか」と見えますね。
2011年05月23日
手になじむ、木製の靴べら

ほぼ毎日のように使っているモノのひとつに、靴をはく
ときに使う「靴べら」があります。
「靴べら」は靴をはこうとする、その瞬間だけ使うので1回に
おそらく5秒ぐらいしか手にもっていない瞬間系道具。
イザっという時に、迷うことなくサッと手のなかへ。
手にもつのが瞬間だからこそ、手になじんで持ちやすく。
カタチを見たら「存在の役割り」がすぐにわかる形をして
この靴べらだと、靴をはく作業がわずらわしい事もなく
まったくストレスを感じない、ストレスフリーな靴べら。
太いグリップ部分から、背中をそったように先端の薄さまでの
造形デザインが信頼できる「存在感」をあらわしています。
この造形のラインに信頼感をただよわせ、つきあい始めて
もう25年ぐらいになる。頼りがいのある靴べらです。
信頼感を別の言葉で言い換えるなら、よけいな心配や不安を
感じることがないから、ストレスフリーの意味にもなると
この靴べらを見て感じますね。
2011年05月16日
和みの樹さんのなごむ木の器
武雄市若木の家具作り塾に行くようになってから、木工家のYさんが
作っている、「和みの樹」と名づけられた木製品を知った。
なんといっても素材が木ですから、日本の暮らしにはかかせない
もうそれだけで、あたたかみのある材料です。
フィンランドの建築家、アルヴァー・アアルトが設計したヘルシンキのデパートの
扉の取っ手が木製なのは、冬の時期でも取っ手をつかむとき、冷たさを
感じないように配慮している。ほんとに木はやさしい素材です。
汁椀のかたちは、大らかな丸みをおびて、こんなゆたかなお碗で食べると
お椀の中の具が何であれ、囲んだ回りを暖かくしてくれるにちがいない。


木工作業場の隅には、作っている木工品を展示する小さな部屋があり
モノと同様に、ほっとする空気につつまれたなごむ空間です。
作っている、「和みの樹」と名づけられた木製品を知った。
なんといっても素材が木ですから、日本の暮らしにはかかせない
もうそれだけで、あたたかみのある材料です。
フィンランドの建築家、アルヴァー・アアルトが設計したヘルシンキのデパートの
扉の取っ手が木製なのは、冬の時期でも取っ手をつかむとき、冷たさを
感じないように配慮している。ほんとに木はやさしい素材です。
汁椀のかたちは、大らかな丸みをおびて、こんなゆたかなお碗で食べると
お椀の中の具が何であれ、囲んだ回りを暖かくしてくれるにちがいない。
木工作業場の隅には、作っている木工品を展示する小さな部屋があり
モノと同様に、ほっとする空気につつまれたなごむ空間です。
2011年04月13日
薄い木のカップと超薄いガラスコップ

今年の1月から体験した家具作り塾で、木に長く触っていたせいか
デザイン雑誌を見ていても、つい木工品に目がいってしまいます。
写真は木の厚みが2mmの木製カップ。名前は「KAMI・かみ」。
陽に向けると、まるで紙のように薄くて透けるそうだから。
北海道の旭川で木工作りをしている高橋工芸さんが作っています。
ロクロで2mmの厚さまで削るには、北海道のセンという木材だから
できるとはいえ、削る技術がともなわないと、そう誰でも簡単には
作れそうにはないような気がします。
素材が木材なので、中に熱い飲み物を入れても手に持てるし
きっと口当たりもやさしいにちがいないでしょう。
こんなに薄い木のカップを見て思い出したのが、ガラスの「うすはり」。

薄さではここまでするんかいと、思うぐらいに「かよわい」薄さの
ガラス製コップです。手に持つと軽いというよりも、ちょっと力を
いれたら割れそうなぐらいにうすいのには、ほんとに驚いた。
白熱電球ガラスを作る技術をコップ作りに応用しているから薄い。
形はいたって普通なコップでも、薄いのでなく超~うすいとなると
これはもう話はかわって、グ~ンと価値が高くなるようです。
2011年04月04日
伊万里鍋島焼の青磁の食器
4月1日(金)から5日(火)まで、伊万里鍋島焼の里・大川内山で
「春の窯元市」が開催され、先週まで冷え込んでいたけど、窯元市の
時期に合わせたように桜の花も満開状態に咲き、見頃になってます。
そこで今日は伊万里鍋島焼の特長のひとつ、「青磁」の器を紹介。
大川内山では青磁鉱石が取れ、「鍋島青磁」は伊万里らしい器です。
写真の小鉢は、上から見ると四角い形をしているのですが、直線を
使わないで、大きな丸みを取り入れた柔らかな形状になっている。

内側の縁周辺には、細やかな彫刻を施して、青磁釉薬をかけると
彫り込んだ所に青磁釉薬がたまり、厚くなる部分とうすい部分で
青磁釉薬の「濃淡」が生まれて、「彫り」が少し強調されます。

青磁小鉢の形状特長のひとつに、縁の面がフラットではなく
ゆるかな上下の曲面に仕上げている点です。
こうしたゆるやかな波のような曲線で囲まれたおかげで、器自体の
存在感と個性がでて、細やかな彫りがさざ波のようにも感じます。
以前、窯業技術センターデザイン部長だったKさんと居酒屋でお酒を
酌み交わしながら、伊万里の焼き物について話をした時に
「青磁釉薬こそ伊万里鍋島焼の個性がでるので、窯元はもっと青磁
釉薬の美しさを研究をし、今の暮らしに合う青磁の食器を作らんば」
と、意見が一致したことがある。
青磁を作る窯元にとっては青磁の器は見慣れた、見飽きているでしょうが
今の暮らしに合う青磁の食器はまだ開発の余地が充分にあると思います。
そのためには、窯元自身が「食の風景」をどう楽しめるかであり
食の風景を楽しむには、どんな器がいいだろうと試しに作ることです。
「春の窯元市」が開催され、先週まで冷え込んでいたけど、窯元市の
時期に合わせたように桜の花も満開状態に咲き、見頃になってます。
そこで今日は伊万里鍋島焼の特長のひとつ、「青磁」の器を紹介。
大川内山では青磁鉱石が取れ、「鍋島青磁」は伊万里らしい器です。
写真の小鉢は、上から見ると四角い形をしているのですが、直線を
使わないで、大きな丸みを取り入れた柔らかな形状になっている。

内側の縁周辺には、細やかな彫刻を施して、青磁釉薬をかけると
彫り込んだ所に青磁釉薬がたまり、厚くなる部分とうすい部分で
青磁釉薬の「濃淡」が生まれて、「彫り」が少し強調されます。

青磁小鉢の形状特長のひとつに、縁の面がフラットではなく
ゆるかな上下の曲面に仕上げている点です。
こうしたゆるやかな波のような曲線で囲まれたおかげで、器自体の
存在感と個性がでて、細やかな彫りがさざ波のようにも感じます。
以前、窯業技術センターデザイン部長だったKさんと居酒屋でお酒を
酌み交わしながら、伊万里の焼き物について話をした時に
「青磁釉薬こそ伊万里鍋島焼の個性がでるので、窯元はもっと青磁
釉薬の美しさを研究をし、今の暮らしに合う青磁の食器を作らんば」
と、意見が一致したことがある。
青磁を作る窯元にとっては青磁の器は見慣れた、見飽きているでしょうが
今の暮らしに合う青磁の食器はまだ開発の余地が充分にあると思います。
そのためには、窯元自身が「食の風景」をどう楽しめるかであり
食の風景を楽しむには、どんな器がいいだろうと試しに作ることです。
2011年03月28日
イタリア・アレッシィのスプーン
ほぼ毎日のように使っているスプーンです。
使いやすく作られているから、気に入ってほぼ毎日使ってます。
写真のスプーンに出会うまでは、今まで使っていたのが使いやすいと
思い込んでいたのに気付かされた。
一般的にスプーンの形状は「たまご型」や「楕円型」が多くあり
それはそれで使っていても別段、特に困ることはないのですが
特に困ることが無いから、といってそれがベストだとは限らない。
モノ作りをしていると、作るのが仕事ですから、作り方に「慣れて」
「モノの使い方・在り方」がおろそかにならないようにせんばです。
写真のスプーンは使い方と、作り方の双方のバランスがとれています。



スプーンのすくい方、微妙な角度と、たまる部分の膨らみなどが
シンプルに、そして絶妙にデザインされています。
デザイナーはイギリス人のジャスパー・モリソン氏で、作っている
メーカーはアレッシィ・イタリア。
2011年02月28日
和樹・なごみのきのやさしい木のヘラ
家具作り塾のすぐ隣りには木工品を作っている「和樹・なごみのき」さんの
木工工房があり、木製のスプーンやヘラ、カップなど、いろいろ作っています。

テーブルの上には、いろんな形をしたヘラが置いてありました。

ヘラを横から見たら、写真のように、わずかに凹みがあり反ってます。
こういう、わずかな凹みやソリがあると、すくうのにも使いやすそうで
手仕事ならではの、やさしいヘラです。
ヘラなどの木工品は特注も受けているそうですから、お気に入りのヘラが
ほしい人は相談しては。⇒和樹・なごみのき
木工工房があり、木製のスプーンやヘラ、カップなど、いろいろ作っています。

テーブルの上には、いろんな形をしたヘラが置いてありました。

ヘラを横から見たら、写真のように、わずかに凹みがあり反ってます。
こういう、わずかな凹みやソリがあると、すくうのにも使いやすそうで
手仕事ならではの、やさしいヘラです。
ヘラなどの木工品は特注も受けているそうですから、お気に入りのヘラが
ほしい人は相談しては。⇒和樹・なごみのき
2011年01月19日
保温力が高いサーモスのマグカップ
こんなに寒い日が続くと、体を温める料理や熱い飲み物の
回数がふえてきますが、せっかく体を温めても部屋の中はまだ寒く
熱いコーヒーをマグカップに入れても、2~3分も過ぎると
もうぬるくなってます。
今日の写真は魔法瓶の業界で100年の老舗カンパニー
「サーモス」のマグカップ。
サーモスの商品は保温力が高い機能性とデザインで人気があり
保温力が高いという機能の裏づけには、「断熱」の技術力。
魔法瓶で培った「真空断熱技術」が基盤にあります。
サーモスはその強みである「真空断熱技術」をベースに、暮らしに
合わせた商品を開発しており、やはり「自社の強み」の軸が
ぶれないことが商品開発には大事です。
サーモスのマグカップはステンレス素材をメインにしているせいか
見た目はゴツイ感じですが、保温力なら俺に任せておけよと
云わんばかりの信頼感もあり、丈夫系なデザインに仕上げています。
それに見た目よりも、持った時に「軽いね~」と意外性もあり
やはり手に持つ道具は、重さのデザインも大切です。
マグカップの形状を見ると、フランスのガラス・デュラックス社の
ピカルディを何となく連想しますが、手に持つカップで「丈夫系」の
同じコンセプトになると、形状も少しは似てくるのでしょうが
サーモスのマグカップは独自のデザインに仕上げています。
2010年09月21日
伊万里の鍋島青磁のビアカップ

伊万里の焼き物は伊万里焼だろうと思う人が多いようですが、伊万里焼と
いう呼び名の焼き物はなく、正しくは「伊万里鍋島焼」。
江戸時代、佐賀鍋島藩の御用窯として、徳川家や諸大名への献上品を
作っていたので、一般には手に入らなかった焼き物が「鍋島焼」。
伊万里鍋島焼には、「色鍋島」や「鍋島青磁」、「鍋島染付」などがあり
特に、鍋島青磁はヒスイのような緑色した釉薬が特長です。
青磁釉薬は食器の生地が薄いと、「釉薬のかかり」も薄くなるので
しっかり青磁釉薬をかけている伝統的な鍋島青磁の湯呑みを持ってみると
ちょっと重く感じる。
実際に白磁の湯呑みと比較して、重量をはかったら明らかに重かった。
若い人ならコーヒーカップが多少重くても、気にしないだろうが、中高年に
なると筋力が低下してくるので、「重さ」が気になります。
伊万里鍋島焼の里・大川内山に来る観光客は、中高年の女性が多いので
食器の「重さ」も、買うか買わないかを判断する材料になるのでは。
窯元さんたちは焼き物に慣れているから、重さに対してあまり気にはせずに
鍋島青磁はこういうものだからと、伝統にこだわってます。
写真の青磁のビアカップは、縁回りに行くほど生地が薄くなっているから
青磁釉薬のかかりも薄いので、上から下へと、緑色のグラデーションに
なってます。釉薬がうすい分だけ、重さも軽くなっているからビールを
飲むときには、あまり重さを感じなくて使い易い。
またビアカップの内側は白い(かけ分け)ので、飲み物の色も楽しめる。
青磁釉薬の「使い方」やデザインを工夫するなど、今の暮らしにもっと
役立つ、楽しくするような食器ができるんじゃないかと思います。
2010年09月14日
成長する椅子

この椅子が我が家にやって来たのは、長女が生まれた時から。
赤ちゃんの頃から、同じテーブルで一緒に食事をするときに
使っていた長女専用の椅子でした。
そして、幼稚園から小学校、中学、高校と身長が伸びるのに合わせ
座面を下にずらしては使い、子供の成長に合わせてくれた椅子。
子供の成長に合わせて、座面の高さを調節できるのは、両側の柱の
内側に彫られた「ミゾ」のおかげで、2枚の板が座面と足載せになる。
長女が大学を卒業して一人暮らしをするようになってから、今では
私が使って、まだまだ現役。いいモノは長く使える見本ですね。
この椅子は「トリップ・トラップ」と云って、ノルウェーで生まれて75年近い。
赤ちゃんや子供を対象に商品を提供しており、商品と顧客対象を絞り込んで
展開している、良い見本ですね。詳しくは青文字部分をクリック
2010年07月29日
折る刃のカッターナイフ
今では紙を切る時にペーパーナイフよりも、カッターナイフをよく使います。
ナイフの切れ味が鈍くなったら、その刃先を折れさえすれば、まるで新品と
同じような切れ味が、すぐに生まれますからね。
カッターナイフの代表メーカー「オルファ」の名前の由来が、刃を折る事から
「折る刃」となり、「オルハ⇒オルファ」となったと聞いてます。
この商品が生まれるキッカケが、ガラスの破片と板チョコのブロックとは。
今では世界中で、文房具からプロ仕様のナイフまで幅広く使われてます。
画期的なのは、刃先が「替刃式」。消耗する刃先だけを交換する合理性。
ナイフは切れなくなると、研石で研いでいたのですが、その手間をなくして
刃先を折って、替刃式にしたことで、利便性がグ~ンと高まりました。
既存商品の不便さを「改良」した成果が、世界に広がったのですね。
カッターナイフの誕生秘話は ⇒ オルファ
2010年07月07日
これは何でしょうか。

ワールドカップは4ヶ国の準決勝になり、ウルグアイとオランダでは
オランダが決勝戦に進み、スペイン対ドイツの勝者と。
準々決勝でのドイツの試合を見ていると、どうもドイツが決勝戦に
残りそうな予感がします。あまり当てにならない予感ですが。
ところで写真のモノを見て、何かすぐにわかる人は少ないのでは。
それと、すぐにわかるの「すぐ」っていうのは、一体何秒ぐらいだろう。
写真は、ある物を研ぐための道具で、そのある物とは「ハサミ」。
これは、ハサミの刃先を研ぐための道具で、ドイツ製です。
もう買ってから10年以上になるけど、なかなかの優れモノ。
右にある2箇所の細長い所に、ハサミを開いて入れて、刃先を研ぐように
なっていて、左手で押さえやすいように親指を置くところだけが、ほんの
少し凹んでいるデザインになっています。この凹みがポイント。
安全性に配慮されて、シンプルなデザインに仕上げてます。
ハサミが主役ですから、ハサミ研ぎのように脇役的な商品というか
サポート品があると主役のハサミの切れ味が良くなりますから
小さいとはいえ存在感があり、ドイツはあなどれないですね。
2010年06月29日
小さな鉛筆削り

時々、机の上で使っている文房具に「鉛筆削り」があります。
白いプラステックにステンレスの片刃をねじで止めたシンプルな構造。
シャープペンもあるから、わざわざ鉛筆を削らなくてもすむけれど
鉛筆削りで鉛筆を削っていくと、削れて木の香りが微かにするのと
スケッチを描く前の一種の儀式みたいにして、描く準備運動のように
削る作業をするのが、いいですね。
そして、自分の好きな鉛筆のとんがり具合を確かめながら、鉛筆を
削る作業をすることで、次の動作(スケッチ)へのはずみにもなる。
こんな小さな道具ですが、指に持ちやすいように、指が当たる所は
凹んでおり、さらにすべりにくくするために、小さなギザギザがある
おかげで、しっかりと持つ事ができ、ここにもデザインがあります。